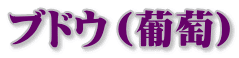
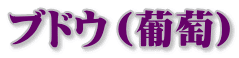
| ブドウ ヨーロッパの文化はワインと共に世界に広がる  ブドウは、ブドウ科 ブドウ属の蔓性落葉低木である。ブドウ属の植物は数十種あり、北アメリカ、東アジアに多く、インド、中東、南アフリカにも自生種がある。日本の山野に分布するヤマブドウ、エビヅル、サンカクヅル(ギョウジャノミズ)もブドウ属の植物である。現在、ワイン用、干しぶどう用または生食用に栽培されているブドウは、ペルシアやカフカスが原産のヴィニフェラ種と、北アメリカ原産のラブルスカ種である。 ブドウは、ブドウ科 ブドウ属の蔓性落葉低木である。ブドウ属の植物は数十種あり、北アメリカ、東アジアに多く、インド、中東、南アフリカにも自生種がある。日本の山野に分布するヤマブドウ、エビヅル、サンカクヅル(ギョウジャノミズ)もブドウ属の植物である。現在、ワイン用、干しぶどう用または生食用に栽培されているブドウは、ペルシアやカフカスが原産のヴィニフェラ種と、北アメリカ原産のラブルスカ種である。ブドウの利用は、新石器時代にまで遡ることが知られている。ジョージアで発掘された約8000年前の陶器の壺が科学分析により世界最古のワイン醸造の痕跡であると2017年に発表された。また、アルメニアでは約6000年前のものとされる世界最古のワイン醸造所跡が発見されており、その頃には既に高度な醸造技術が確立されていた。さらに、1996年に現在のイラン北部にて7000年前のワインの容器が発見された。この発見は、メソポタミア人や古代エジプト人が、ブドウの栽培とワイン醸造の技術を持っていた証拠である。中国でのブドウの栽培とワイン造りは、2世紀の漢王朝が大宛(だいえん:現在のウズベキスタンにあった国)からヴィニフェラ種を輸入してから始まった 。しかし、それ以前から、中国の野生のブドウのエビヅルでワイン造りが行われていた。日本では、古来から山梨県で栽培されている甲州種が日本産ブドウでは唯一のヴィニフェラ種(東洋系)である。だが、その由来については現在も不明な点が多い。 注:現在、甲州種はDNA解析の結果、カスピ海付近で誕生したヴィニフィラ種が中国に渡り、長い年月をかけて中国の野生種との交雑を経て、 リースリング 日本に渡ってきたと考えられるようになった。 ワイン文化がヨーロッパへ広まったのは、現在のレバノンが位置する地中海岸沿いを拠点としていたフェニキア人によってである。まず、フェニキア人により古代ギリシアに伝わる。この頃は水割りにして飲まれ、原酒のまま飲む行為は野蛮とされた。これは当時の上流階級が、ギリシャ北方に住むスラブ系の祖先であるスキタイの原酒飲酒の習慣を忌み嫌っていたからだと言われている。ワインはそこから地中海沿岸を経て古代ローマへと伝わり、ローマ帝国の拡大と共にガリアなどの内陸部にも水割り文化と共に伝わっ ていった。当時のワインは、ブドウ果汁が濃縮されかなりの糖分を残している一方、アルコール度数はそれほど高くなかった。今日の蒸留酒を飲む時に行うようなアルコール度数を抑えるための水割りではなく、過剰な甘さを抑えるための水割りであった。ヨーロッパの水は硬水が多く大変飲み難いものであったので、それを飲みやすくするためにワインは必要不可欠なものであり、その意味では水で割るというよりも、水に添加して水を飲みやすくする物であった。 ワイン製造の技術が格段の進歩を遂げたのはローマ時代においてとされ、この時代に現在の製法の基礎が確立した。それにより糖分がかなりアルコールに転化され、ワインをストレートで飲むようになった。また、ローマはガリア(現在のフランスと周辺の地域)を征服した後ガリア人から木の樽の使用を学んだ。ワインはそれまで陶器や土器の瓶や壺に貯蔵していたが、楢(なら)、樫(かし)、櫟(くぬぎ)などの樽に詰めるとワインは熟成し、ふくよかな香味を生じるようになった。  中世ヨーロッパでブドウ栽培とワイン醸造を主導したのはキリスト教の修道院であった。イエス・キリストがワインを指して自分の血と称したことから、ワインはキリスト教の聖餐式において重要な道具となった。ただしこの時代、ワインは儀礼として飲むものとされ、むやみに飲んで酩酊することは罪とされていた。中世後期(12世紀頃)にはワインは日常の飲み物として広まるようになっていた。また、ブルゴーニュワインが銘酒として有名となったのはこの頃からである。ルネサンスの時代以降、娯楽としての飲酒が発展する。17世紀後半、醸造や保存の技術、また瓶の製造技術が向上し、ワインの生産と流通が飛躍的に拡大した。 中世ヨーロッパでブドウ栽培とワイン醸造を主導したのはキリスト教の修道院であった。イエス・キリストがワインを指して自分の血と称したことから、ワインはキリスト教の聖餐式において重要な道具となった。ただしこの時代、ワインは儀礼として飲むものとされ、むやみに飲んで酩酊することは罪とされていた。中世後期(12世紀頃)にはワインは日常の飲み物として広まるようになっていた。また、ブルゴーニュワインが銘酒として有名となったのはこの頃からである。ルネサンスの時代以降、娯楽としての飲酒が発展する。17世紀後半、醸造や保存の技術、また瓶の製造技術が向上し、ワインの生産と流通が飛躍的に拡大した。
大航海時代が始まり、世界各地にヨーロッパ人が植民するようになると、移民たちは故郷の味を求め、ワインを製造するために入植先にブドウを植えていった。ヨーロッパブドウは世界各地に広がった。スペイン人がチリにブドウの木を導入すると、オーストラリアも1788年にブドウの栽培を開始している。 1850年代にはニュージーランドのホークス・ペイにあったカトリック教会がブドウ園を開き、いまでは同国で最古のブドウ園となっている。 さらにブドウの木がアメリカに導人されると、ワイン醸造は同国の一大産業となり、合衆国はフランス、イタリア、スペインにつぐ世界第4位のワイン生産国となった。 現在、ブドウの生産量の7割がワイン用である。 作品はリースリング(Riesling)、白ワイン用ぶどう品種と長野県東部町で作られた東部巨峰。 |