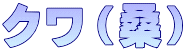
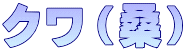
 夕焼け小焼けの あかとんぼ 夕焼け小焼けの あかとんぼ負われて見たのは いつの日か 山の畑の 桑の実を 小籠に摘んだは まぼろしか 十五で姐やは 嫁にゆき お里のたよりも たえはてた 夕やけ小やけの 赤とんぼ とまっているよ 竿の先 童謡「赤とんぼ」を作詞した三木露風(1889~1964年)は、5歳の時に両親が離婚して、祖父の家に預けられ幼少期を過ごした。「赤とんぼ」は、幼少期のおぼろげな思い出を綴ったものだ。 小籠に摘んだ桑の実はおやつ代わりだったのか。口の中に広がる甘酸っぱい味が母のいない切ない日々の思い出と重なっている。 6月になると桑の実は黒く熟してきて、食べごろになる。美術館の周りにも何本かの桑の木があり、手の届くところにも実をつけている。しかし、中には実のつけない木もある。植物図鑑を調べると、クワは雌雄異株または同株とある、雄株だけの木もあるので実をつけないわけだ、また、木によって実の大きさが違っている。大きな実のなる木はハチジョウグワである。ヤマグワの変種で、伊豆半島から伊豆七島に分布する。 「赤とんぼ」の山の畑は、桑畑だろうか。明治から昭和の初期まで養蚕業は日本の一大産業に成長していた。 カイコは東アジアに生息するクワコという蛾を家畜化したものと考えられている。だが、どのようにして家畜化したのか分かっていない。 カイコ(カイコはカイコガの幼虫)はクワの葉を餌にする。中国では最初に丈夫そうな野生のクワを植え、生長したところで、それを台木にして別に栽培した苗木を接ぎ木していた。接ぎ木から5年たつとクワの葉を収穫することができ、その葉を細かく切ってカイコに与えた。 まずはじめに、カイコガの卵を集め一斉に孵化するように注意深く飼育する。孵化したカイコは網の上に広げた切りワラの床の上にのせられ、それから35日間カイコはクワの葉をむさぽり食う。この期間の終わり頃になるとカイコは繭をつくる。この繭を集めて一部は繁殖用に利用し、他のものは熱い蒸気の蒸し風呂か熱湯に浸けて中の幼虫を殺す。中を空にした繭を今度は丁寧にほぐしながら1本の絹糸にしていく。長さは1500メートルにもなる。この絹糸を染め、パターンを織りこみながら生地にする。こうした全行程もクワがなければ始まらない。たとえばシルクのブラウス1枚には4キロ以上のクワの葉が必要になる。 絹の生産は紀元前3000年頃の中国で始まっていた。伝説によれば黄帝の后・西陵氏が絹と織物の製法を築いたとされ、一説には紀元前6000年頃ともされる。少なくとも前漢の時代には蚕室での温育法や蚕卵の保管方法が確立していた。6世紀半ば、北魏の『斉民要術』によれば現在の養蚕原理がほとんど確立していた事が判明している。 一方、他の地域(国)では絹の製法が分からず、非常に古い時代から絹は中国から陸路でも海路でもインド、ペルシア方面に輸出されていた。これがシルクロード(絹の道)の始まりである。荷馬やラクダを使ってこのルートを定期的に往復する商人は、他に紅茶や紙、スパイスそして陶器も積みこんで西へ旅した。チベット仏教もこのシルクロード沿いに伝わり、商人はブドウやガラス、香料、牛の飼い葉にする乾し草を積んで東へ戻った。それでもシルクがもっとも価値ある商品であることは変わらず、シルクが貨幣として使われることも多かった。シルクひと綛(かせ:輪形に結束した糸)が馬1頭か奴隷5人分と見積もられていた。紀元前1000年頃の古代エジプト遺跡から中国絹の断片が発見されている。紀元前1世紀にシルクがローマ帝国の中心地まで届くと、ローマ人はシルクを宝石のように扱った。絹は上流階級の衣服として好まれた。紀元前1世紀にエジプトを占領すると絹の貿易を求めて海路インドに進出、その一部は中国に達した。だが、ローマでは同量の金と同じだけの価値があるとされた絹に対する批判も強く、アウグストゥスが法令で全ての人間の絹製の衣類着用を禁止した。それでも絹着用の流行は留まることはなかった。 ローマ時代の作家大プリニウスは著書『博物誌』(西暦77年)で伝説の木の収穫について解説を試みている。「最初にこの作業にたずさわったのはセレス(シルクの生産者の意味で、中国人のこと)で、かの地は羊毛になる木があることで知られる」と説明した。さらに「その木の葉に水をまいて白い軟毛を分離し、女性が糸を撚り出し、ふたたび織り上げる作業を行った」と述べている。中国の人々は秘伝のシルク製造を西洋に知られないようにしていた。蚕のことも蚕が唯一食べる桑のことも秘密にしていた。そのためシルクの製造法について常に噂がたえなかった。シルクが特定の木で見つかる白い軟毛からできるという作り話は、たしかに野生のカイコガの様子にもっとも近いものではあった。ローマではそろそろシルクが十分出まわるようになり、裕福な市民はシルク製の立派なドレスを着るようになっていた。 6世紀に絹の製法は、キリスト教ネストリウス派(カトリックから異端とされ、唐の都・長安で伝導し、景教と呼ばれ多くの中国人信者がいた)を通じて、東ローマ帝国に入った。中世ヨーロッパでは1146年にシチリア王国のルッジェーロ2世が自国での生産を始め、またヴェネツィアが絹貿易に熱心で、イタリア各地で絹生産が始まった。フランスのフランソワ1世はイタリアの絹職人をリヨンに招いて絹生産を始めた。リヨンは近代ヨーロッパにおける絹生産の中心となる。ちなみに宗教改革で母国を追われたプロテスタントの絹職人を受け入れたイギリスでは、ジェームズ1世以来、何度も絹の国産化を計画したが本国で蚕を育てる事に悉く失敗し、1619年に漸く成功に漕ぎ着けた植民地もまたアメリカ合衆国として独立した。このため、他のヨーロッパ諸国よりも中国産の良質な生糸を求める意欲が強く、これが英清間の貿易不均衡、更にはアヘン戦争へと繋がっていく遠因となったとする説もある。 日本にはすでに弥生時代に絹の製法は伝わっており、律令制では納税のための絹織物の  生産が盛んになっていたが、品質は中国絹にはるかに及ばず、また戦乱のために生産そのものが衰退した。このため日本の上流階級は常に中国絹を珍重し、これが日中貿易の原動力となっていた。明代に日本との貿易が禁止されたため、倭寇などが中国沿岸を荒らしまわり、この頃東アジアに来航したポルトガル人は日中間で絹貿易を仲介して巨利を博した。鎖国後も中国絹が必要だったため、長崎には中国商船の来航が認められており、国内商人には糸割符が導入されていた。 生産が盛んになっていたが、品質は中国絹にはるかに及ばず、また戦乱のために生産そのものが衰退した。このため日本の上流階級は常に中国絹を珍重し、これが日中貿易の原動力となっていた。明代に日本との貿易が禁止されたため、倭寇などが中国沿岸を荒らしまわり、この頃東アジアに来航したポルトガル人は日中間で絹貿易を仲介して巨利を博した。鎖国後も中国絹が必要だったため、長崎には中国商船の来航が認められており、国内商人には糸割符が導入されていた。
長年の衰退の影響で日本国内産の蚕は専ら真綿の生産にしか用いる事が出来ない劣悪なものが多く、西陣や博多などの主要絹織物産地では中国絹が原材料として用いられていたが、鎖国が行われ始めた寛永年間から品質改良が進められた。また、幕府は蚕種確保のため、代表的な産地であった旧結城藩領を天領化し、次いで同じく天領で、より生産条件の良い陸奥国伊達郡に生産拠点を設けて蚕種の独占販売を試みた。これに対して仙台藩、尾張藩、加賀藩といった大藩や、上野国や信濃国の小藩などが幕府からの圧力にも拘らず、養蚕や絹織物産業に力を入れたため、徐々に地方においても生糸や絹織物の産地が形成された。この結果、貞享年間(1685年)には初めて江戸幕府による輸入規制が行われた。更に同幕府の8代将軍徳川吉宗は貿易赤字是正のため、天領、諸藩を問わずに生産を奨励し、江戸時代中期には日本絹は中国絹と遜色がなくなった。このため、幕末の開港後は絹が日本の重要な輸出品となった。 養蚕業、製糸業は明治以降の日本が近代化を進める上で、重要な基幹産業であり、殖産興業の立役者のひとつである。この時に富岡製糸場が建てられた。ほぼ前後して清(中国)でも製糸業の近代化が欧米資本及び現地の官民で進められた。元々国内での需要と消費が多く、生産者も多かった日中両国での機械化による生産量の増大は、絹の国際価格の暴落を招き、ヨーロッパの絹生産に大打撃を与えた。 第二次世界大戦で日本、中国、ベトナムなど東アジア諸国との貿易が途絶えたため、欧米では絹の価格が高騰した。このためナイロン、レーヨンなど人造繊維の使用が盛んになった。戦後、日本の絹生産は衰退し、現在は主に中国からの輸入に頼っている。1998年の統計では、日本は世界第5位の生産高ではあるが、中国、インド、ブラジルの上位3ヶ国で全世界の生産の9割を占め、4位のウズベキスタンも日本を大きく引き離している。2010年現在では、市場に提供する絹糸を製造する製糸会社は、国内では2社のみとなっている。この結果、日本の桑畑は大幅に減少した。 クワの木質はかなり硬く狂いも少ないので良材とされ、老人の杖や床柱に利用された。磨くと深い黄色を呈して美しいので、しばしば工芸用にも使われる。しかし、銘木として使われる良材は極めて少ない。特に良材とされるのが、伊豆諸島の御蔵島や三宅島で産出される「島桑」であり、緻密な年輪と美しい木目と粘りのあることで知られる。また古くから弦楽器の材料として珍重された。正倉院にはクワ製の楽琵琶や阮咸が保存されており、薩摩琵琶や筑前琵琶もクワ製のものが良いとされる。 |