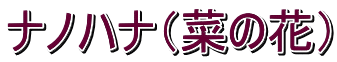
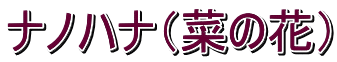
 ナノハナ(菜の花)は、アブラナ科アブラナ属の植物の花の総称であり、アブラナ、カブ、ハクサイ、キャベツなどの花はすべてナノハナである。花は茎の先に総状花序をつけ黄色の倒卵形の4枚の花弁を十字状に密集して咲く。 ナノハナ(菜の花)は、アブラナ科アブラナ属の植物の花の総称であり、アブラナ、カブ、ハクサイ、キャベツなどの花はすべてナノハナである。花は茎の先に総状花序をつけ黄色の倒卵形の4枚の花弁を十字状に密集して咲く。また、ナノハナの中で主として花を食するものを菜花(なばな)といい、ナタネ、カブ、ハクサイ、キャベツなそがある。 菜の花畑に 入日薄れ 見わたす山の端 霞ふかし 春風そよ吹く 空を見れば 夕月かかりて 匂い淡し 叙情豊かな歌は、情景が瞼に浮かぶようだ。この唱歌「朧月夜」に歌われた菜の花畑は何の花だろうか。 この唱歌を作詞した高野辰之は長野県豊田村(現在の中野市)の出身で、若い頃に隣の飯山市で小学校の教員をしていた。飯山市や中野市を含む長野県の北信地方一帯は江戸時代から菜種栽培が盛んで、春には一面の菜の花畑が広がっており、高野はその光景を歌に詠んだと想定される。 江戸時代には、植物油の採油を目的としてアブラナ(油菜)が栽培され、種子から油を絞り出した。その油は菜種油と呼ばれた。菜種油は、主に灯油原料に利用され、生活に密着したものとなった。そのため、菜種という言葉は、一般的な植物(作物)名として定着した。しかし、明治になってより収量の多いセイヨウアブラナに取って代わった。したがってこの歌の菜の花はセイヨウアブラナの畑である。 昭和30年代以降、菜種油の需要が減ると菜種の作付けは激減し、長野県の北信地方では菜の花畑はほとんど見られなくなった。しかし、近年は観光用にノザワナ(野沢菜)を大規模に栽培して「朧月夜」で歌われた情景を再現している。飯山市では連休中に見ごろとなるよう、ノザワナの播種日を調整している。 菜種油は日本の食用油の6割を占めており、生産は北海道が約7割を占めている。長野県は1%弱である。食用としての菜花の生産は三重県がトップで全体の約3割を占め、東京、新潟と続き、この三都県で全体の5割を占めている。長野県は6%ほどで第6位である。ところが漬菜(漬物にする葉物野菜)は長野県がトップであり、そのほとんどが野沢菜である。 伝承によると、野沢菜は野沢温泉村の健命寺の住職が宝暦年間(1751~1754)頃に、京都に遊学し、帰省に際し、天王寺蕪の種子を持ち帰って植えたところ、葉が大きく成長したので蕪ではなく漬菜として利用したのが起源だという。 カブは日本には中国を経由して渡来した西日本型と、シベリアを経由して渡来した東日本型の2種類がある。天王寺蕪は西日本型であるが、野沢菜はDNA解析から東日本型であることが分かった。 アブラナ(和種ナタネ)の原種はブラシカ・ラパという雑草である。冷涼なトルコ高原の原産で、寒さに強く、低温下でも速く生長する特徴をもつ。この原種が栽培植物になり、和種ナタネ、ハクサイ、カブ、タイナ(体菜)、ミズナ、キョウナなどの作物が生まれた。 日本にはいつ頃に渡来してきたのだろうか。最終氷河期が終わった約1万年前の縄文時代早期の地層からはアブラナ科植物の花粉は検出されていないが、縄文時代前期(約7000~5000年前)の福井県鳥浜貝塚の地層からアブラナ科の種実が出土している。しかし微量である。弥生時代、古墳時代とこの状況が続き、奈良時代になって増えてくる。奈良時代の後半(8世紀)になって栽培が始まったと思われる。 奈良時代には既に漬物が存在していたことが知られる。アブラナ科植物の場合は、カブやダイコンなどの根茎部分を漬ける場合と、カブナの葉や茎の部分を漬ける場合とに大別される。いずれとも、塩や麹などと併用することにより、保存性があってかつ主食との相性のよい食品として、食文化の中で必要不可欠な存在となっていった。  アブラナ属に所属する種は30種ほどであるが、多くが自家受粉しない自家不和合性(自分の雄しべの花粉で雌しべが受粉しない)を持つ虫媒花である。 このため、種間交雑が生じやすい性質を持ち、属間交雑も生じている。農業や園芸分野ではそれらをもとに多様な栽培品種が作出されている。 日本では和種ナタネ、カブなどから各地方で伝統野菜(九州の高菜、広島菜、長野の野沢菜、大阪の天王寺かぶ、京都の聖護院かぶ、滋賀の日野菜かぶ等々)が生まれていった。 鮮やかな黄色の花をつける菜の花は切り花としても利用される。千利休は特に菜の花を好んだため、利休忌には必ず菜の花が使われる。 しかし、菜の花は花付きが粗く切り花には向いていない。日本でチリメンハクサイを改良し、花付きのいいハナナが作出された。 チンゲンサイの菜の花 |