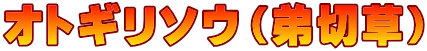
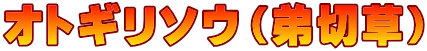
 大室山のリフト乗り場から、海に向かって舗装された坂道を下ってくる。ここは朝の散歩コースの一部である。早朝とはいえ、7月の日差しはすでに強く、まぶしい。道路の右側に溝があり、溝の向こう側は大室山の山裾が続き、草が生い茂っている。この草叢でいつも季節を感じる花に出会う。しかし、この時期は花も少ない。時々チダケサシが穂を並べて咲いている。ツユクサが青花を開いている。 大室山のリフト乗り場から、海に向かって舗装された坂道を下ってくる。ここは朝の散歩コースの一部である。早朝とはいえ、7月の日差しはすでに強く、まぶしい。道路の右側に溝があり、溝の向こう側は大室山の山裾が続き、草が生い茂っている。この草叢でいつも季節を感じる花に出会う。しかし、この時期は花も少ない。時々チダケサシが穂を並べて咲いている。ツユクサが青花を開いている。草丈40cmほどで、茎の先に2㎝足らずの黄色い5弁花をつける花を見つけた。オトギリソウである。漢字で書くと「弟切草」。実におぞましい名前である。 名前の由来は平安時代の伝説に基づく。 花山院[かざんいん:第65代天皇(在位:984-986年)]の時代に、藤原為頼という鷹匠がいた。鷹の傷を治すことにかけては並ぶ者がなく、どんな深手でも家伝の薬を使えば立ちどころに癒えた。もちろん、その製法は長子相伝の門外不出であった。 そのころ、仲間の鷹匠の蔵人経忠は、花山院からとくに命じられて大事な鷹の世話をしていたが、負わせてしまった傷がどうにも回復せず困リはてていた。蔵人経忠の娘と恋仲だった為頼の弟為房は、父の不運に胸を痛める恋人を見かね、ある夜処方を盗みだして教えてしまう。 激怒した為頼は、ひざまずいて詫びる弟を一刀のもとに切り殺してしまった。以後、家伝の効能あらたかな薬草は世の人々の知るところとなり、弟切草と呼ばれるようになった。 石井由紀「伝説の花たち」 この話には娘も後追い自殺したという異説もある。 江戸時代の「和漢三才図会」には少し違った話が掲載されている。 その昔、花山院の時代に、晴頼(せいらい)と呼ぶ一人の鷹飼かあった。其業に精しいことは将に神に入るというほどであった。若し鷹が傷を被るようなことでもあると、秘かに何処からか草を取って来てこれにつげるのであったが、すると不思議にもその傷はたちまち癒る。人はその草の名を乞い問えども晴頼はこれを秘して決していわなかった。然るに家に居る弟がこの名薬を独り秘めておくべきものでないと、ひそかにこれを洩らした。晴頼はこれを大いに憤ってこの弟を殺してしまった。これよりこの草を誰いうとなく、弟切草と名づけたということである。そしてある人は弟切草の葉の黒点は、弟を切った時の血潮が残ったのだともいっている。 いずれにしろ秘密を漏らした弟を斬り殺したという話が元である。 オトギリソウはオトギリソウ科オトギリソウ属の多年草で、日本全土の山野に自生し、7-9月に、黄色い五弁花をつける。一日花である。 オトギリソウの葉や花などに腺体があり、この腺体に色素が含まれている場合には黒点(油点ともいう)といい、これが連なると黒線、色素を含まない場合には透かすと明るく見えるので、明点という。 この黒点の正体は、ヒペリシンという光作用性物質で、これを摂取した後に日光(紫外線)に当たると皮膚炎や浮腫を生じる。 ヨーロッパではオトギリソウの黒点をキリストの脇腹から滴った血の跡とも、首をはねられた聖ヨハネの血とも言う。聖ヨハネ祭の前夜(6月24日)にはこの花を摘んで花輪を編み、家の屋根の上に投げたり戸口や部屋の中に吊すなどして魔除けとした。 伝説のとおり、茎や葉は止血などの民間薬として使われてきたもので、生薬名はない。基本的には薬草であり、タカノキズグスリ(鷹の傷薬)、チドメグサ(血止め草)など悪さをイメージしない異名も持つ。地上部の全草が薬草として利用され、開花期または結実期などに、花や果実がついたままの茎葉を刈り取り、日干し乾燥させたものを小連翹(しょうれんぎょう)と称して用いる。 粗刻みした小連翹を、1日量10 - 15g 、約400 - 600 ccの水で30分ほど、半量になるまで煎じた液が利用される。のどの痛み、風邪の咳、口内炎、扁桃炎、歯痛には煎じ液をうがい薬として利用したり、切り傷、腫れ物、湿疹、かぶれには患部に煎じ液を直接塗るか、冷湿布するなどの利用方がある。また、消毒用エタノールに浸してチンキとする。地方によっては、遮光瓶に新鮮な食用油とともに花がついた生のオトギリソウもしくは、小連翹を一緒に入れて浸しておき、虫刺され、おでき、切り傷、軽い火傷に直接塗る民間療法がある。 茎葉に、やや多量のタンニンが含まれており、薬用としてはタンニンの効用が期待されている。タンニンには、組織細胞を引き締める収斂作用(しゅうれんさよう)があり、細胞が傷ついて出血しているときのような場合には、引き締めて止血する働きをする。このため切り傷などに貼り薬や塗り薬として処方した場合には高い効果を発揮することが期待できる。 |