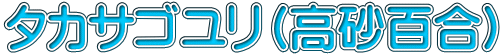
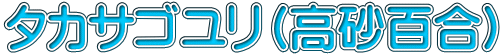
 美術館の周辺では、ヤマユリが咲き終 タカサゴユリはテッポウユリの変種とされ、台湾が原産地である。タカサゴは台湾の古称である高砂(たかさご)国に由来する。台湾では台湾ユリという。タカサゴユリはテッポウユリに似るが、茎が比較的太く丈夫で、丈が 30㎝ほどから高いものは1.5m ほどに生長するものもある。花の長さは 15-20cm、直径は 5cm より大きめと、テッポウユリよりも大型になる。また葉が細く長さは15㎝ほどで茎に密についている。このことから、ホソバテッポウユリとも呼ばれる。花被片は6枚で、花は横向きだが少し下に傾くことが多いとされる。 花は白を基調とするものの外側に薄い紫色の筋が入る。この紫色の筋がはいることがタカサゴユリの特徴で他のユリと区別できる。ただ中には筋のあまり目立たないものやほとんど筋がなく白のものもある。タカサゴユリはテッポウユリとの交雑種が多く、変異も多いと思われる。テッポウユリと交雑し、この筋のないものをシンテッポウユリということもある。テッポウユリよりも花は小さく、葉が細いのが特徴で、花は夏の終わり頃に咲き、タカサゴユリともよく似ているが、タカサゴユリは花の外側に紫色の筋があるので見分ける事ができる。シンテッポウユリは種が飛んで野草化しているが白色の美しい花を咲かせる。別名で「ナツユリ(夏百合)」と呼ぶこともある。 シンテッポウユリも自家受粉で種ができ、種まきで1年もせずに開花させる事ができる。 タカサゴユリが増えているわけは? タカサゴユリは、テッポウユリから進化したと考えられている。テッポウユリは、園芸用のユリとして有名だが、もともと沖縄など南西諸島の海岸近くに分布する野生のユリである。この南西諸島の海の向こうに台湾があり、タカサゴユリが分布しているのである。 テッポウユリは海岸に自生する野生植物であるが、雑草として広がることはない。ところが、テッポウユリから進化した夕力サゴユリは、雑草として広がっている。この違いはどこにあるのだろうか。 もっとも大きな違いは、種子から花が咲くまでの期間である。 現在、園芸種として改良されているテッポウユリは、球根で増やされており、種子はつけないが、野生のテッポウユリは種子で広がっていく。ただし、テッポウユリは種子が芽生えて花が咲くまでに3年の期間を必要とする。ところが、タカサゴユリは種子からわずか一年足らずで花を咲かせることができるのである。 また、テッポウユリの花粉を媒介するのは、スズメガという蛾である。テッポウユリは闇の中で目立つ白い色をしているし、夕方になると香りが強くなる。こうして、夜に活動するスズメガを呼び寄せる。しかし、スズメガがいない環境では受粉することができない。 一方、タカサゴユリは自殖によって種子を作ることができる。タカサゴユリは、花びらの付け根がくっついていて、花が咲き終わると、花びらが雄しべや雌しべを包み込むようにして、地面に落ちる。このとき、雄しべと雌しべがくっついて、自家受粉を行うのである。 それだけではない。テッポウユリは一つの花が種子を100個くらいしかつけないのに対して、タカサゴユリはその10倍の1000個もの種子をつける。こうして、タカサゴユリは次々に花を咲かせ、大量の種子をまき散らして増殖していくのである。 このようにテッポウユリと比べるとタカサゴユリは、雑草として優れた性質を持っている。テッポウユリからタカサゴユリヘの進化の過程で何が起こったのかはわからないが、タカサゴユリは、ユリの仲間としては珍しい雑草となった。 ただし本種はいわゆる連作障害が出やすいと言われ、一時的に根付き拡がっても数年経つと姿を消す場合が多い。ただ、美術館の周辺で毎年、十数本が固まって咲いている所があるが、今のところ姿を消す様子がない。 種子を多く付けたタカサゴユリは、新たな原野を求めて風に乗って種を飛ばして生息域を拡げている。種子が辿り着いた地が生育環境に合致すると、ときに群生して大きな花を咲かせる。 |