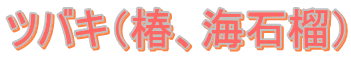
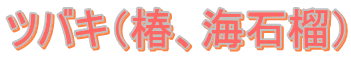
 巨勢山(こせやま)の つらつら椿 つらつらに 見つつ偲ばな 巨勢の春野を 巨勢山(こせやま)の つらつら椿 つらつらに 見つつ偲ばな 巨勢の春野を万葉集の巻1.54の坂門人足(さかとのひとたり)の歌である。歌の意は『巨勢山の椿をじっくり見ながら、椿の花咲く頃の巨勢の春野を偲んでみよう』となる。つらつら椿は花盛りの頃の椿が点点と連なる様を表している。 万葉集の椿はヤブツバキである。ツバキは日本原産で、北海道南西部、本州、四国、九州、南西諸島、国外では朝鮮半島南部と台湾に分布する。 ツバキの語源については ① 「厚葉木(あつばき)」の「あ」が落ちた。(貝原益軒『日本釈名』) ② 「艶葉木(つやばき)」の「や」が抜けた。(屋代弘賢『古今要覧稿』、『大言海』) ③ 「強葉木(つよばき)」の「よ」が抜けた。(松永貞徳の『和句解』) といった説がある。 これらの説に対し、與謝野鉄幹が『日本語原考』で朝鮮語に基づくとしている。朝鮮語でツバキを意味する「冬柏」の古音’Tsu-Pak'(ツーパク)が’Tsu-Baki'(ツーバキ)に転じたとする。 司馬遼太郎が『街道をゆく28・耽羅紀行』で現地ガイドに「冬柏」を発音して貰い、'tong-back’(トンベック)がピヤットと聞こえ、ツバキの音に似ているとしている。 言語学者の中島利一郎も『植物語源考』でこの説を支持している。 上古時代、日本と朝鮮半島との交流が盛んにおこなわれていた。人だけでなく、文物の往来も行われた。4~6世紀には南朝鮮にあった伽耶国に任那日本府が設置されている。秦氏や漢氏などの有力氏族は朝鮮からの渡来人とされる。また、新羅による朝鮮半島の統一は、日本に大きな影響を及ぼした。滅ぼされた百済や高句麗からは多数の亡命者が日本列島へ渡り、新羅からも仏教僧らが逃れて来て、日本はこうした難民を受け入れた。 これらのことから、朝鮮語を受け入れる素地があったと思われる。 ツバキは「椿」または「海石榴」と表記される。 「椿」の字は国訓、もしくは、偶然字形が一致した国字とされる。中国で「椿」はセンダン科のチャンチンを指している。そしてツバキは中国では「山茶」と表記する。 この国訓または国字説に対し、薬学博士の木下武司は『万葉植物文化誌』の中で、漢字が伝えられて200年ほどしか経ていない時代に、国字を作るほどの漢字文化は成熟していたか疑問とし、『荘子』の「逍遥遊編」に記載される大椿(たいちん)という伝説上の長寿の霊木を借用したとも考えられるとしている。 日本書紀によると、王仁(わに)が応神天皇の時代に百済から日本に渡来し、千字文と論語を伝えたとしている。漢字の伝来は4世紀後半から5世紀のはじめと考えられる。当初、大和朝廷の文筆の担当は渡来人を中心に行われたが、しだいに日本人も漢字を習熟し、5世紀には漢字の使用が普及していったとされる。200年もあれば、十分に漢字の成り立ちや仕組みを理解したのではないだろうか。ましてや「椿」という字は木へんに春を付けた字で分かりやすい簡単な字である。「椿」を国訓または国字と考えていいと思う。 「海石榴」の字は中国の文献にも出てくる。「石榴」はザクロのことだが、ツバキの花を見たことがなかった中国の人にとっては、ツバキの珍しい赤い花をザクロの赤い花にたとえたと思われる。「海」が付いているのは、遠い辺境の地や異国から来たことを意味している。隋・唐の首都であった長安は内陸の都市で、海から遠く離れた地にあり、「海」は辺境を意味していた。中東原産のナツメヤシは海棗、南アメリカ原産のデイェゴは海紅豆、ロシアのチョウセンゴヨウは海松と表記した。 日本人とツバキとの関わりは、5000年ほど前にさかのばることができる。福井県三方五湖の縄文時代の遺跡鳥浜貝塚からはツバキの材を利用した石斧の柄が出土しており、ツバキ細工の櫛も発見されている。ツバキの材は堅く緻密なので、このような利用のされ方をした。それ以後も、木槌、木魚、印鑑、楽器、道具類の柄などの細工物に用いられた。 また古代には、冬に葉を落とさないのは魔力をもつためと信じられ、ツバキは神聖な木とされ、また天皇の権威の象徴とされた。『日本書紀』景行紀に景行天皇が豊後の国において土蜘蛛を征伐した際、ツバキの木でつくった槌を使ったとあるのも、ツバキの木の霊力を信じたことを象徴する。ツバキを神木とする神社も各地に見られる。 観賞用としてツバキが使われ利用されるようになったのは室町時代になってからであり、茶花とし  て利用された。さらに豊臣秀吉は茶の湯にツバキを好んで用い、茶道においてツバキは重要な地位を占めるようになる。 て利用された。さらに豊臣秀吉は茶の湯にツバキを好んで用い、茶道においてツバキは重要な地位を占めるようになる。しかし今日のように広く普及するようになったのは、江戸時代になってからである。 サザンカが散るときは花弁が一枚ずつ散るのに対し、ツバキの花は花ごとポトンと落ちる。ツバキも実は離弁花なのだが、花弁の基部が癒着しているため花ごと落ちるのである。このように花が落ちるのを武士の首の落ちるのに結びつけて忌み嫌い、武士は屋敷内にツバキを植えなかったという。 しかし、徳川二代将軍秀忠はツバキを愛好し、国中から集めさせて吹上花苑に植えさせたことにより、一般庶民にも流行しだしたようである。『武家深秘録』の慶長18年には「将軍秀忠花癖あり名花を諸国に徴し、これを後吹上花壇に栽(う)えて愛玩す。此頃より山茶(ツバキ)流行し数多の珍種をだす」とある。 安楽庵策伝による『百椿集』(寛永7年・1630)、烏丸光広『椿花図譜』(寛永11年・1634)には619種のツバキが紹介されている。その後もツバキの図譜や園芸書がいろいろ出版されているが、松平忠晴の『百椿図』(寛永12年)、伊藤伊兵衛三之丞『花壇地錦抄』(元禄8年・1695)には207種、作者不明の『椿花図譜』には720種が記載されている。これだけ多くの品種があったということは、園芸史上でも特記すべきことで、その発達のほども知られる。僅か数十年の間にこれだけの品種が増加したことは、これまた驚くべきことである。これほどに増えたのは、実は延宝年間(1673~80)にトウツバキやチョウセンツバキ系のものが日本に入ってきたからである。 |